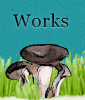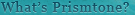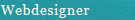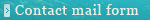2009.02.27 02:17

買い物代行サービス / ECナビコンシェルジュ
http://concierge.ecnavi.jp/
スーパーマーケットの買物代行は知っていたけど、
ファッション関係は、なるほどなという感じ。
前からいくつか似たサービスはあるみたい。
東京とか大都市から離れたところだと、便利なんだろうな、これ。
そういえば薬のネット販売とか話題だけど、
特に島住まいの人とかにとっては、死活問題ですよね。
規制する必要性を感じないんだが。
話は戻して、
ファッション系なら、特に海外向けに展開したらおもしろそう。
色々言語とかシステムとか大変そうだけど。
・・海外から電話一本で注文できるとか。
けどまぁ、
日本の雑誌は読んでないか?っていう、そもそもの問題があるか。
んー、
普通のECサイト(ZOZOとか)が多言語対応するっていう方が、先かな。
とか色々考えながら、何かないかサイトを探すと、
日本商品の海外向け通販サイト
http://jzool.com/
桜花堂SAKURA
http://www.sakurashops.com/
いい感じ。...あら、これネプラがやってるんだ。
転送コム
http://www.tenso.com/landing/jp/
これもネプラ。
ネプラがんばってるなぁ。
海外通販サイトリンク
http://www.post.japanpost.jp/int/link/index.html
EMSによる発送ってことで、日本郵便のサイトで
ちょっとまとまってリンクがあっていい感じ。
思考の記録ってことで。
2009.02.22 03:35
ノートン先生が激重になってかれこれ数ヶ月経ってたんですが、
もう耐えられなくなって、原因究明しようと思い、アドオンを無効化したりしました。
そしたら、
Norton IPS と Norton Toolbarが激重の原因のようでした。
(ツールバーとか非表示にはしていて何も使ってなかったし。。。)
削除してもいいかなと思ったんだけど、無効化するだけでも大分軽くなりました。
ひどいとき、起動に1分くらいかかったのがばかばかしい。ほんとに。
余談ですが、アドオンのFoxmarksがすごい便利です。
google Syncだっけ?あれよりもだいぶいいと思う。
2009.02.05 00:54

Total Solar Eclipse of 2009 july 22、あと半年もないですね。
月食、トカラ(吐噶喇)列島という鹿児島の島々が一番よく見えるそうですが、
行くなら比較的アクセスのいい、奄美かなと思ってます。
飛行機のチケットも取れるとは限らないのに、真剣に行くかどうか悩んじゃってます。
・・・結構行きたいです。
日に日にこの日食の話題は盛り上がっていって、色んな人が奄美やトカラ付近の島に集まってくるんだろうなぁとか、考えてるとワクワクします。
東京でも日食は見られるけど、せっかくなら現地に行って皆既日食を見たい。
そして、コレ↓

奄美皆既日食音楽祭 ECLIPSE 2009
冒頭の画像は、このフェスのTシャツです。
フェスに出演する高城氏も着てましたね。
このTシャツ、渋谷からちょっと歩いた、Global Chillage Tokyoで購入しますた。
あと、CCPというお店にもあるみたい。
いずれもオンラインで購入可。
他もろもろ、近畿ツーリストが頑張ってます。
日食グッツオンラインストア
日本国土での観測46年ぶり! 2009年 皆既日食ツアー
2009.02.04 04:07

So Very Very Nice
先日、NORDICフォント使用したよと、ご丁寧に連絡いただきました。
Newyorkの若いデザイナーさんのようで、他の作品のセンスもいいなぁ。
2009.02.02 00:51

先日1月31日、
社会人のためのボランティア発見サイト『もんじゅ』をリリースしました。
転職求人サイトのように、ボランティアを探し、その場で応募や問い合わせができます。
ボランティアと聞くと、とっつきにくい人も多いとは思うのですが、
いざ僕も深入りしてみたら、ボランティアの関わり方もいろいろだなと思いました。
時間で言えば、
もちろんフルタイムに近いものもありますが、
それこそ時間があいた休日を使ってみたり、
平日の夜にちょこっとやってみたり。
内容で言ったら、
専門職のそれこそデザインをしたり、翻訳、ヘアスタイリスト...etc
特に専門知識も必要ない、イベントスタッフ、事務作業など。
自分にあった関わり方ができるんじゃないかなぁと思います。
また、
自分の視野を広げる為、自分のスキルの経験値を上げる為、
そういう意味もこめて参加してみたら、
Win-Winな関係になるんじゃないでしょうか。
もんじゅは、まだ始まったばかりなので、今後、
掲載数を増やしていって多く選択肢を提供していくと同時に、
個人とNPOやNGOの距離を近づけるような仕組みにしていきたいなぁと思います。